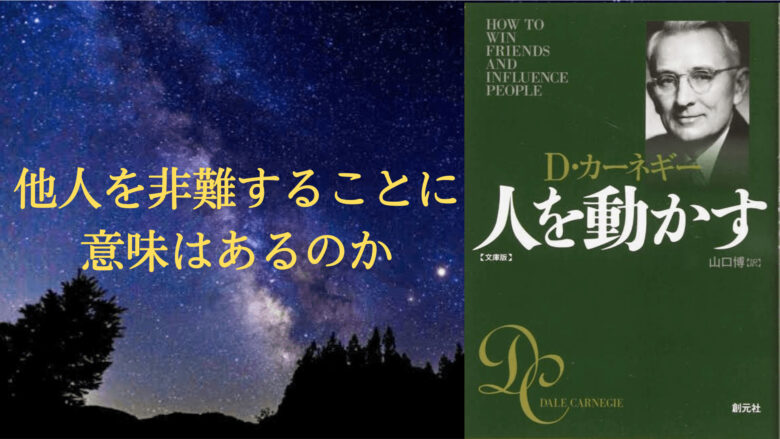本日のひと息読書は、「人を動かす」です。
あらゆる自己啓発書の原点となったデール・カーネギー不朽の名著と言われるほと有名な本です。
「人を動かす」と言う題名から、経営者やチームのリーダーに向けられた本かと思い、読みはじめましたが、そうではありませんでした。
どちらかというとこの本は「心を動かす」と言うことがテーマにあると思います。
我々が生きていく上で、人との関わりは切っても切れない関係にあります。
他人からの怒りを買わず、議論をせず、相手に好かれる。
そんな方法が、たくさんの具体的なエピソードがとともに語られています。
そこで今回は僕が一番大きな影響を受けた「第1章」の話を簡潔にまとめてみようと思います。
盗人には五分の理を認める
「二丁ピストルのクローレン」は、針の先ほどのきっかけからでも簡単に人を殺してしまうほどの殺人鬼です。
「免許を見せたまえ」と言葉をかけた警官に、いきなりピストルで乱射を浴びせた殺人鬼が、”関係者各位”に宛てた手紙の内容はこうです。
「私の心——それは、疲れて果てた心であるが、優しい心である。誰ひとり人を傷つけようとは思わぬ心である」
クローレンがシン・シン刑務所の電気椅子に座るときに、吐いたセリフは「こうなるのも当然だ——大勢の人々を殺したのだから」というものではありませんでした。
「自分の身を守っただけのことで、こんな目にあわされるんだ」
これがクローレンの最後の言葉でした。
この話の要点は、凶悪無類クローレンでさえ、自分が悪いとは全然思っていなかったと言うことです。
似たような考え方をする犯罪者は他にもいます。
「俺は働き盛りの大半を、世のため人のために尽くしてきた。ところが、どうだ——俺の得たものは、冷たい世間からの非難と、お尋ね者の烙印だけだ」
全米を震わせた暗黒界の王者アル・カポネの言葉です。
ニューヨークでも、第一級の悪人ダッチ・シュルツは、自分のことを「社会の恩人だ」と称しています。
シン・シン刑務所長は言いました。
「自分のことを悪人だと考えている受刑者はほんとどいない」
上記のように、極悪人たちでさえも、自分が正しいと思い込んでいるとすれば、彼らほど悪人ではない我々は自分のことを一体どう思っているのだろうか。
我々はどうあるべきか
アメリカの偉大な実業家ジョン・ワナメーカーは言いました。
「30年前に、私は人を叱りつけるのは愚の骨頂だと悟った。自分のことさえ自分で思うようにならない。天が万人に平等な知能を与えたまわなかったことにまで腹を立てたりする余裕はとてもない」
他人のあら探しをすることは、何の役にも立ちません。
相手はすぐさま防御体制を敷き、何とか自分を正当化しようとします。それに、自尊心を傷つけられた相手は結局、反抗心を起こすことになり、むしろ自分に害を及ぼしかねません。
「我々は他人からの賞賛を強く望んでいる。
そして、それと同じ強さで他人からの非難を恐れる」
偉大な心理学者ハンス・セリエ の言葉です。
「人を動かす」には、「ものを動かす」と同じような感覚で考えてはダメです。
「人」を「もの」と考え、自分の思いのままに動かそうとすると失敗します。
「人」は「人」であり、それぞれがそれぞれの考え方を持っている。
そこに上も下もなく、それぞれが「正解」であり「不正解」でもある。
「自分の考え」を正当化しようとするのではなく、自他ともに正当化することを忘れてはならない。
「『人』を動かす」
とてもよく考えられた題名だと感じました。
まとめ
最後に本書に出てくる、とてもわかり易い比喩を一つ紹介します。
「人を非難するのは、ちょうど天に向かって唾をするようなもの」
他人を非難すると必ず我が身に返ってきます。
あなたが他人に唾を吐きたいとき、その唾を飲み込む勇気こそ、我々が「人を動かす」上で最も重要なことなのかもしれません。